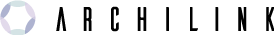建物で火災が起きた際に、火と共に発生するのが大量の煙である。
煙はまたたくまに建物内を覆いつくし、避難者の避難行動を妨げる。
煙は、避難者が体に吸い込むと有毒であると共に、視界を妨げ、避難方向さえも、見えなくさせてしまう。
このような避難活動において妨げたになる煙を排除するための設置を排煙設備という。建築基準法でいう排煙設備は大きく「機械排煙設備」と「自然排煙設備」に分類することができる。
今回題材として扱う、排煙窓は「自然排煙設備」として定義されるものである。排煙窓設置における留意点をまとめていきたい。
設置基準
まず、排煙設備の設置基準について法文を確認しておきたい。
建築基準法施行令 第126条の2
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。) 、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの (建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。)
三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分
四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの
上記要件に該当する場合は、排煙設備の設置を必要とする。ただし、法126条の2 1項5号に定めるように、国土交通大臣が定める告示に該当する場合は、設置をしないことができるので確認が必要である。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
排煙設備の技術要件
前喝したような条件に合致していない場合は、排煙設備を設置する必要があるのだが、排煙設備には「自然排煙設備」「機械排煙設備」の2種類が存在する。
ここでは、「機械排煙設備」と「自然排煙設備」の解説を記していくが、本題である「排煙窓」としての「自然排煙設備」を重点的に解説していく。
①機械排煙設備は、排煙するために、煙を排出する排煙機器そしてその煙の通り道となる風道(ダクト)によって構成されている。
排煙機器は吸引力は違うが、換気扇をイメージしてみればよいかと思う。ダクトの先などに換気扇がついておりその圧力により、煙を吸引し外に排出する仕組みである。
まず、排煙口(吸込口)は、防煙区画の各部分から30m以内となるように1か所設置しなければならない。そして、風道(ダクト)は 排煙機又は給気機に接続され保安上必要な強度、容量及び機密性が要求される。
ダクト内の煙の熱により周囲への延焼などの影響が予想される場合は、ダクトの断熱や可燃物との隔離等の措置を講じなければならない。排煙機を操作するものとして、手動起動装置が必要となる。
防煙区画ごとに該当区画が見渡せる位置で火災発生時に容易に操作できる場所に設置する。80cm以上150cm以下に取り付け、排煙口の手動起動装置であることを表示する。
そして排煙機は以下の能力を有するものが必要であると規定されている。消防活動拠点の場合は、240㎥/min以上。特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用する場合は360㎥/min以上の能力。
消防活動拠点以外の部分において、建物の規模等により300㎥/min以上。複数の防煙区画に接続されている場合は600㎥/min以上の能力又は120㎥/min又は当該防煙区画の床面積に1㎥/minを乗じた能力か、(複数の防煙区画に接続されている場合は2㎥/min)いずれか大きい方を選択となっている。
②自然排煙設備は、煙が上昇することを利用した、窓をあけることによる排煙方式である。一般的に煙は空気よりも軽く上部に向かって上昇する。
また、天井部や壁画上部に設けらた窓が開いていると、押し出されるように煙は排出される。自然排煙の設置基準も「建築基準法施行令第 126 条の 2」で規定されている。
また、自然排煙口(排煙窓)および手動開放装置の構造・機能などについ ては、「建築基準法施行令第 126 条の 3」で規定されている。
居室の自然排煙口の開口面積
直接外気に接する自然排煙口(排煙窓)は「防煙区画部分の床面積の50分の1以上」の開口面積を有すること。防煙区画部分の各部分からの水平距離が30m以下に設置すること
自然排煙口の設置場所
隣地境界との関係
自然排煙口(排煙窓)隣地境界線から25cm以上かつ1階分の排煙の有効開口面積の合計面積以上離れていなければならない。また、屋上部分に、屋根の出がある場合は、その先端から隣地境界線までの距離が、上記条件を満たしていなければならない。
天井との関係
排煙に有効な部分は、施行令120条の3の3において、天井高さが3m未満の場合において、天井面より80cm以内を排煙上有効な部分として定めている。
また、天井高さが3mを超える場合においては、天井高さの1/2以上かつ、3m以上の部分を排煙上有効な部分として定めている。
例えば、天井仕上をルーバ天井などとしている場合その部分を天井面とみるか等は建築主事の確認が必要であろう。
煙はルーバを超えて、懐内にもぐりこんでしまう、煙をより早く排出することを考えると、煙が昇りきった部分に排煙口がついているのが理想であるが、鉄筋コンクリート造ラーメン構造などの場合は一般的に梁が下がってきていることが多く、開口を設けられないなどの問題が生じる。
その場合は、見上げのスラブなどに開口を設けるなどが考えられる。
排煙窓の開口形式と有効開口面積
●天井面から下方に 80 cm以内にある自然排煙口としての回転窓・内たおし窓・外たおし窓及びガラリについて、開口部面積(S)と有効開口面積(So)の関係 は、回転角度(α)に応じて次の算定式により扱う。
- 90°≧α≧45°のとき So=S
45°>α≧ 0° のとき So=α/45°×S
●引き違い窓・片引き窓・上げ下げ窓は、開口部を有効開口面積とする。ただし、排煙上有効な部分内とする。
手動開放装置について
●操作位置について
・壁に設ける場合:床面から80cm以上1.5mの高さ
・吊り下げて設ける場合:床面からおおむね1.8mの高さ
●表示について
・表示:見やすい方法でその使用方法を表示
・自然排煙口の構造について
自然排煙口について
- 材質
・煙に接する部分は、不燃材料であること
排煙窓は、一般的にガラス窓などで構成されるので、不燃材料の要件を満たしている。ちなみに建築基準法では、不燃材料の定義として、建設省告示1400号において定められている。
構造
・常時は閉鎖状態とすること
・開放時は、排煙に伴う気流や外風で閉鎖されない構造であること
・火災時でも脱落しないこと
手動開放装置の操作について
- 操作方法
○現地手動
・単 純 手 動:窓を直接手で開放(引違い窓、開き窓、回転窓などで、施行令第 126 条の 3 第 5 号で規定される高さの位置に手掛けなどがある場合)
・機械的手動:ワイヤーなどを介して開放(ラッチ方式、手動オペレーター式)
・電気的手動:電気信号などにより開放(電動オペレーター方式)
○遠方手動
・電気的手動:電気信号などにより開放(電動オペレーター方式)
○煙感知器連動
・電気的手動:電気信号などにより開放(煙感知器連動オペレーター方式、電動オペレーター方式)
○構造
・現地手動による場合、単一動作で操作できること
・操作は、単純で力が弱い人でも容易に操作できること
・自然排煙口を自然換気で使用する場合、使用頻度が高くなるため、ワイヤーなどの部品の調整が容易であること
・遠方手動、煙感知器連動の場合は、中央管理室に表示するための端子が必要
・電動オペレーターの場合は、予備電源が必要
引違窓などを、排煙窓として取り扱う場合においては、クレセントの高さ位置が重要になってくる。
施行令第 126 条の 3 第 5 号においては、手動解放装置について床面から80cm以上150cm以内と定めている為、腰窓部分などを排煙窓として扱う場合には、高さの指定をしておかないと、容易に150cmを超える部分でクレセントを設置されてしまう可能性があるので注意したい。
設置のポイント
排煙設備を設置する際の検討方法はまず、防煙区画内の床面積の1/50を自然排煙口となる窓等でとることができるのかがポイントになる。中には、窓に面しない居室などもあることであろう。
その場合は告示による不燃区画等の形成で、緩和できないかを考えて行く。それでもクリアできない場合は、面積の細分化や2室排煙などを考えてクリアできないかを模索していく。
機械排煙の機器をもうける場合は、費用等のバランスを考えて、方向性を定める必要がある。排煙性能を考えていくと機械排煙にする方が望ましいのだろうが、機械の故障などメンテナンスも頻度高く行って行かなければならない。
そのように考えていくと、まずは自然排煙口を設けることで対処できないかを考えることが先決であろう。自然排煙口についても、排煙専用の窓を居室上部に設けるなどをよくするが、プラン上の制約などから、上部排煙窓を設置しにくい状況にあることも考えられる。
排煙窓というと、手動開放装置付きつまりオペレーター付きの排煙窓をイメージしがちだが、普通に扱う引き違い窓においても排煙窓の役割は果たすことができるので、確認をしておきたい。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
最後に
いかがであっただろうか、排煙窓一つにおいても、様々な規定が存在し制約もあることが理解いただけたかと思う。
排煙窓は、非常時において使うものであるのでしっかりと機能することが必要である。竣工後の日常的なメンテナンスが必要となるのは当然であるが、設計時点においては、メンテナンスを極力せずに維持できる方針つくりは重要である。
また、法規上は手動解放装置部分の平面的位置は定められていないが、避難時を想定した容易にボタン等を押しやすいような位置に配置することが望ましい。
当然施設利用者は、家具などを置きたくなるので、その配置も含めた計画が設計時点から行うことが重要になってくる。

一級建築士
不動産コンサルティングマスター
一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。