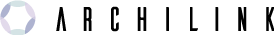「延焼ライン」や「延焼線」、「延焼のおそれのある範囲」、これらは正確には法規上の用語ではない。
建築基準法にある用語は「延焼のおそれのある部分」であり、「延焼ライン」などの用語は、その範囲を図面上で示すものであるが、事実上「延焼のおそれのある部分」とほぼ同義で用いられているものである。
ここでは、延焼ラインについて、その定義や注意点を解説する。
なお、ここでは「延焼ライン」として解説をすすめていくが、法文の引用などではとうぜん「延焼のおそれのある部分」とする。二つの用語の関係としては上記の通りとして理解していただきたい。
延焼ラインの定義
まずは延焼ラインに関する、法文上の定義について確認しておこう。延焼のおそれのある部分については、建築基準法の第2条、用語の定義にて規定されている。該当する条文を以下に示す。
建築基準法
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
第6号 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
(後略)
以上となる。上記の法文を簡単にまとめると、以下の通りとなる。
○ 基準線は隣地境界線・道路境界線・建築物間の中心線
○ 基準線から1階は3m以内、2階以上は5m以内
○ 空地・水面等に面した部分には適用されない
上記のようなかたちで規定されているものが、延焼のおそれのある部分である。
なお、余談となるが、法文上の延焼ライン、1階は3m・2階以上は5mという数値については、延焼限界曲線や延焼危険曲線などと呼ばれる、延焼危険範囲を示す計算式に基づくものである。
これは一般的に「高さ=係数×離隔距離の2乗」で表わされ、断面で表わすと逆放物線のカーブとなる。このことからも、2階以上が一律の距離であることが理解できるだろう。
ただし、この計算式の考え方からみると、高さの基準が地盤面からの高さでなく、階による規定であることは疑問である。そうした意味では、たとえば吹き抜けにおいて、2階部分に相当する部分の考え方について、これは法規上の規定がないが、おのずと判断ができるだろう。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
延焼ラインの取扱いについての4つの注意点
延焼ラインについては、法文の解説で示した通り、隣地境界線・道路中心線・建築物相互の外壁間中心線からそれぞれ距離を測るよう規定されている。
ただし、隣地の利用状況や、建築物相互の外壁が平行でない場合、建築物の規模が異なる場合、地階についてなどは別に取り扱いが規定されている。以下、これら4つのポイントについて、順に解説する。
線路敷及び公共水路・緑道等の取扱い
日本建築行政会議では、「建築物の防火避難規定の解説」において、線路敷・公共水路・緑道について別に取扱いを規定している。簡単にまとめると、以下の通りである。
○ 線路敷:ただし書の防火上有効な公園・広場・川等の空地とみなして延焼ラインの適用なし
○ 公共水路・緑道:道路と同様に扱い、中心線を延焼ラインの基準とする
この理由についての解説を、以下に引用する。
「鉄道の線路敷については令第135条の4(北側斜線の緩和)や令第135条の12(日影規制の緩和)において道路や水面等と同様に扱われており、道路斜線についても昭46住街発第1164号で公園や水面等と同様に緩和してもよいとされているように、建築物が建築される可能性も少ないため、延焼のおそれのある部分の扱いにおいても防火上有効な空地に類するものとして扱ってもよいこととした。
また、公共の用に供する水路や緑道についても、公的な管理に属するものであれば建築物の敷地として使用される可能性はなく、空地として半永久的に確保されると考えられるので、延焼のおそれのある部分について緩和してもよいと解する。
ただし、水路については幅が10m以上あれば明らかに防火上有効であるが、これより狭いものについては暗渠として道路のように使用される場合もあり、防火上の観点から道路等と同様にその中心線から算定することができることとした。」
ここで注意したい点は、空地とみなされる線路敷の定義である。道路斜線で参照されている通達、住街発第1164号「線路敷に係る敷地の斜線制限の取扱いについて」(昭和46年11月19日)によると、駅舎部分については建築物とみなして斜線の緩和が認められていない。
したがって、「建築物の防火避難規定の解説」においても、空地とみなされる線路敷は「鉄道の線路敷(駅舎等駅構内に面する部分は除く。)」と表現されている。
建築物相互間の取扱い
法文においては、同一敷地内の2以上の建築物相互間の延焼も想定して、延焼ラインの距離を規定している。この建築物相互間については、その外壁間の中心線からの距離によることとされているが、外壁面が平行でない場合や外壁面の長さが異なる場合について、日本建築行政会議が「建築物の防火避難規定の解説」において取扱いを規定している。
それによると、建築物相互の外壁が平行でない場合には、それぞれの外壁線を延長し、その交点での角の二等分線を外壁間中心線とするのが一般的である。外壁面の長さが異なる場合も考え方は同様である。
短いほうの外壁面の短部で接する隣の外壁面と、長いほうの外壁面とのなす角度の二等分線を外壁間中心線とする。
附属建築物の取扱い
敷地内に複数の建築物があれば、必ずすべてにおいて延焼ラインが生じるわけではない。法文では、複数の建築物の延面積合計が500㎡以内であれば、それらの建築物は、一つの建築物とみなすとされている。すなわち延焼ラインは生じない。
また、規模や用途によっては、そもそも2以上の建築物とみなさないような取扱いも規定されている。これも日本建築行政会議が「建築物の防火避難規定の解説」において規定しているものである。以下に解説文を引用する。
「附属建築物のうち自転車置場、平屋建の小規模な物置(ゴミ置場も含む。)、受水槽上屋、屎尿浄化槽及び合併浄化槽の上屋、ポンプ室で主要構造部が不燃材料で造られたもの、その他の火災のおそれが著しく少ないものについては、法第2条ただし書の「その他これらに類するもの」として取り扱い、本体建築物においては延焼のおそれのある部分を生じないものとする。
なお、小規模な物置の開口部については、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(両面20分の防火設備。以下同じ。)を設けること。」
ここであげられている用途については、それ自体が火災の発生のおそれが少ない用途であり、また、不燃材料で造られていることから、他の建築物からの類焼も想定されないことにより、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁と同等のものとして取り扱うものである。
ただし、小規模な物置の具体的な規模については、本体建築物の用途・規模等によってそれぞれ判断されることであり、審査機関との調整が必要であるとされている。
また、不燃材料で造られた屋外階段・開放廊下・バルコニーの部分についても、法2条第6号ただし書きの「その他これらに類するもの」として取り扱い、同一敷地内の他の建築物においては延焼のおそれのある部分を生じないものとするという取扱いが示されている。
地階の取扱い
法文における延焼のおそれのある部分は、「1階」と「2階以上」のそれぞれに対してその範囲を規定している。ここで問題となるのが、法文に規定のない地階の取扱いである。
というのも、建築基準法上では地階であっても、地上部分にその外壁や開口部を有する場合があるからだ。地階の定義である、施行令第1条第2号を以下に示す。
(用語の定義)
施行令第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
第2号 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。
(後略)
すなわち、法規上は地階であっても、その天井高さの2/3までは地盤面から上にあるという地階が存在するわけである。とうぜん、地盤面上の2/3部分には外壁があり、開口部を有する場合もある。
その場合の外壁・開口部等の取扱いが問題となるが、日本建築行政会議は、「建築物の防火避難規定の解説」において、地階については延焼のおそれのある部分は規定上生じないとしたうえで、上記のように、地盤面上に地階の外壁・開口部等がある場合は、「延焼防止上、地階についても1階とみなし、延焼のおそれのある部分を算定する必要がある。」としている。
すなわち、地階にも延焼ラインが適用されるわけである。ただし、地盤面下でドライエリアになっており、そのドライエリアの壁等に対面して、防火上有効に遮られているとみなされる部分についてはこの取り扱いから除外される。すなわち延焼ラインの対象とはならない。
しかし、ドライエリア上端より上部にある部分はこの取り扱いから除外されるものではない。この取り扱いについては、ドライエリアをなす壁を地盤面上に立ち上げた場合や、逆に1階の床レベルが地盤面よりも下にあり、壁や開口部の一部がドライエリア内にある場合など、いろいろなケースが想定される。
これについては法文のただし書き「耐火構造の壁その他これらに類するもの」との関係も考えられるので、審査機関との打ち合わせが必要であろう。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
延焼ライン内における防火上の措置
ここまで解説してきた延焼ライン、すなわち延焼のおそれのある部分は、それ自体ではただ建築物の一部を指定する用語にすぎない。
法の目的はそれらの部分を指定し、その建築物の構造・規模、計画地の防火地域指定などに応じた、防火上の措置を規定することにある。
延焼ライン内での、各部位に求められる主な防火上の措置は極めて多岐にわたる。簡単にまとめると、以下の通りとなる。
防火設備とみなすそで壁・塀等
延焼ライン内で求められる防火上の措置の一つに、開口部における、「防火戸その他の政令で定める防火設備」の設置がある。これについては、施行令第109条第2項において、外壁・そで壁・塀その他による防火設備のみなし緩和が規定されている。まずは施行令の条文を下記に示す。
(防火戸その他の防火設備)
施行令第109条
第1項 法第2条第9号の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第2号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の3までにおいて同じ。)及び法第64条の政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。
第2項 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から1階にあつては3m以下、2階以上にあつては5m以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
すなわち、外壁・そで壁・塀等で遮ることができれば、それら外壁・そで壁・塀等が防火設備とみなされ、遮られた開口部そのものは防火設備でなくともよいということである。
なお、これら外壁・そで壁・塀等については、告示第1369号においてさらに規定されている。以下に引用する。
建設省告示第1369号「特定防火設備の構造方法を定める件」(平成12年5月25日)
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。
特定防火設備の構造方法を定める件
第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
(中略)
5 建築基準法施行令第109条第2項に規定する防火設備とみなされる外壁、袖壁、塀その他これらに類するものにあっては、防火構造とすること。
(後略)
また、これら外壁・そで壁・塀等による遮り方については、日本建築行政会議が「建築物の防火避難規定の解説」において明確にしている。解説文を引用すると、以下の通りである。
「延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部と隣地境界線、道路中心線又は延べ面積の合計が500㎡を超える2以上の建築物相互の外壁間の中心線(以下「隣地境界線等」という。)との間にあって延焼のおそれのある部分を遮る耐火構造、準耐火構造又は防火構造の外壁、そで壁、塀等(以下「防火そで壁等」という。)で、開口部の四隅から、1階では3m、2階以上では5mの半径で描いた球と隣地境界線等との交点で囲まれた範囲をすべて遮ることができるものは防火設備とみなす。」
隣地からの延焼ラインにかかりやすく、かつ防火設備とするのが難しい開口部(たとえば住宅の木製玄関ドアや駐車場のパイプシャッター、共同住宅等のゴミ置場引き戸など)については、ここで解説したみなし防火設備による緩和が有効に活用できるだろう。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
最後に
延焼ラインに関する規定じたいは極めてシンプルなものであり、それによって特定される、延焼のおそれのある部分に関する防火上の措置も、明解に規定されている。
ただし、延焼ラインの基準となる境界線等、とくに複数の建築物がある時の、建築物相互の外壁間の中心線については、十分な注意が必要である。計画内容に応じて、確認申請の審査機関との事前の打ち合わせが重要である。

一級建築士
不動産コンサルティングマスター
一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。