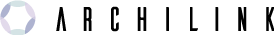地下室に音楽室や書斎をつくるなど、静かな空間を作りだすには絶好の場所である。
しかし、新築の場合であれば当初より計画をすることで、問題なく実現が可能であろうが、増築の場合となると検討が必要であろう。
増築といえば一般的に考えるのが、地上部において左右に増やすか、上部に階を増やすなどが考えられる。地下の増築はほとんど聞いたことがないのではないだろうか。
しかし、まず法的には要件を満足すれば、問題はない。ただ技術的にどう行うのかは疑義がある。
ここでは、技術的な観点も考慮しながら、どのように行っていくのかも解説をしていきたいと思う。
地下室って増築できるの?
地下室の増築という観点からから考えられるのは、建物の直下に建てるのか、もしくは建物の位置とずらして建てるのかということが考えられる。
まず、建物直下に建てる場合であるがこれは非常に難しいのではないかと考える。地上階に建物がある場合、地盤面に程近くに基礎がありそこから地盤面に力が伝達し、建物を支えている。
直下部分に地下室をつくる場合は、この基礎部分を撤去や利用等をして地下室を築造する計画となるので、工事中において地上部分が自立して建っていることができるように施工計画を建てなければならない。
不可能とまではいかないと思うが、工事中は地上階に人は入居できないなど、また地上階を安全に支えることができる工事検討などが必要となり、工事費や工事日数など要するのは間違いないであろう。
続いて、既存建物と平面的な位置をずらして地下室をつくるということを考えてみる。これは、前述した、建物直下に設けることよりははるかに作りやすいものであると考える。
具体的にどのように進めていくかというと、配置上地下部分を作る場所を開削し、地下室を築造するというだけである。この時注意しなくてはいけないのは、増築であるので基本的には既存棟と取り合う部分が出てくるはずである。
その部分をつくる際には既存部分の改造等が必要となる。また、敷地が狭い場合などは、山留を設けたり、既存棟と近接をしている場合には転倒しないための検討などが必要となるであろう。
また、地下室に共通して言えることであるが、地面からの漏水が考えられるので、止水対策も重要である。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
意識しなければならない法的ポイント
続いて、地下室増築の際に注意しておかなければならない、法的なポイントについて記していきたい。
建築面積はカウントされるのか?
まずは、建築面積の定義を確認しておきたい。
(建築基準法施行令第2条第2号)
建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
冒頭部分を見ていただきたい、「地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。」との記載がある。つまりは、地盤面にすべて埋まっている地下部分は無条件で建築面積算入外である。
続いて、地盤面に1mを超えて地下部分が露出している場合は、建築面積に参入される。
基本的には建築面積は算入されないとの考えで、計画を進めて問題はないだろうが、既存との接続部分などに、階段を設ける場合などに建築面積のカウント部分が存在する可能性がある。
新築時に建蔽率いっぱいで計画をしている場合に、まったく余裕がない場合などは無理となることも考えられるので、意識しながらの計画を進めるべきであろう。
床面積はカウントされるのか?
床面積は建築基準法において、「壁等で囲まれる面積」を指すが、普通に考えたら床面積はカウントされそうである。原則はその解釈で問題はない。
だが一部、決められた用途における場合のみ、容積率算定における床面積のカウントから除外できる規定があるので紹介をしておきたい。
(建築基準法52条3項)
3 第一項・・・・(中略)
の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。
以下にこの法文が示す部分の解説を記す。
「住宅、老人ホーム等の用途において、延床面積の1/3を限度として地下部分の床面積を算入しないことができる」
具体例をあげていきたいと思う。
たとえば、専用住宅で1階および2階がそれぞれ60平方メートル、地階が30平方メートルだとすれば、その合計150平方メートルの3分の1は50平方メートルであり、地階がまるまる除外されることになる。
また、1階および2階がそれぞれ50平方メートル、地階が80平方メートルだとすれば、その合計180平方メートルの3分の1は60平方メートルであり、地階のうちこれを超える20平方メートル(80-60)が加えられて、容積率算定上の延床面積は120平方メートルである。
地下室を築造する際に一般的には大きくつくることは考えないであろう。法における1/3という大きさはこれを考慮して考えられているのではないだろうか。
注意してもらいたいのは用途限定があるということである。「地下室は1/3まで床面積に入らない」という頭で覚えてしまうと、用途を失念していたが為に、本来作れない地下室を作れると解釈してしまう。絶対に避けたいミスだ。
また、細かい話であるが、算入されないのは容積率算定上の床面積であり、「基準法が示す床面積には含まれる」ということである。一般的にその他条例等で使用される、床面積のカウントには含まれる可能性があると頭の隅においていただきたい。
地下に居室を設けても大丈夫なのか?
住宅等で地下をつくりたいと考える場合には、娯楽室や音楽室などのいわゆる居室を望むであろう。地下に居室を設ける場合に法規的にはどのように規定されているのかを確認しておきたい。
(建築基準法29条)
(地階における住宅等の居室)
住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
(建築基準法施行令22条の2)
(地階における住宅等の居室の技術的基準)
第二十二条の二 法第二十九条 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 居室が、次のイからハまでのいずれかに該当すること。
イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
ロ 第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
ハ 居室内の湿度を調節する設備が設けられていること。
二 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分(以下この号において「外壁等」という。)の構造が、次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。
イ 外壁等の構造が、次の(1)又は(2)のいずれか(屋根又は屋根の部分にあつては、(1))に適合するものであること。
ただし、外壁等のうち常水面以上の部分にあつては、耐水材料で造り、かつ、材料の接合部及びコンクリートの打継ぎをする部分に防水の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
(1) 外壁等にあつては、国土交通大臣が定めるところにより、直接土に接する部分に、水の浸透を防止するための防水層を設けること。
(2) 外壁又は床にあつては、直接土に接する部分を耐水材料で造り、かつ、直接土に接する部分と居室に面する部分の間に居室内への水の浸透を防止するための空隙(当該空隙に浸透した水を有効に排出するための設備が設けられているものに限る。)を設けること。
ロ 外壁等の構造が、外壁等の直接土に接する部分から居室内に水が浸透しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
まず一般的な地上階部分と同じ考えを持つことは忘れてならない。「採光」「換気」「排煙」基準に応じて満たしていく必要がある。かつ上記基準を満たしていく必要がある。
・増築確認申請などについては、基本的には地上階と同じで、もろもろまとめられている知見があるかと思うのでここでは割愛させていただく。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
地下室増築のケーススタディ
ここでは、地下室増築を実際にどのように実現しているのかの事例を紹介したい。
駐車場部分に地下室を増築
(株)マックライフは<神奈川県横浜市>、リノベーションによって地下室を作りだしている。以下に設計のポイント等を紹介する。
ホームページより抜粋(http://www.macklife.co.jp/renovation/yokohama_t_basement/)
地下室設置でスペースの有効活用 横浜市 T様邸
間取り 1ルーム
完成時期 平成20年2月
ワークスペース 14.62㎡
ドライエリア 5.48㎡
はじめは、既設の建物にお子様の部屋を増築することを計画されていたT様。
いろいろと方法を検討した結果、既設建物の景観を損ねることなく延べ床面積の1/3までが容積率に換算されない地下室を、お庭の駐車スペース下に増築することに。
その地下室はご自宅でお仕事をするお母様のお部屋となりました。
防露対策として、防湿ボードやウレタン吹き付けを施し、外部建具にはスウェーデンの木製3層ガラス入りサッシと木製断熱玄関ドアを用いています。
また、内装はT様のご要望で、床材を天然リノリウム、天井と壁をドライウォール(壁の一部にエコカラット使用)で仕上げました。
建物とは違う平面位置に地下室を作りだしている。既存建物とはつなぐことなく、別棟として地下室を作りだしている様子である。
地下の開削や土留め等の処理は必要になるが、既存建物に対してダメージを与えることなく完成させることができるので、理屈にかなった計画であろう。
また地上部分も有効に利用できているので、効率的な土地の使い方になっているのではないだろうか。
建物直下部に地下室を増築
(株)SHOWA<神奈川県横浜市>は、実績は無いものの、実用新案をもって建物直下部に地下室を増築する方法を提案している。概要としては、基礎直下部にアンダーピンニング鋼管杭を圧入し、山留めで抑えながら地下を築造していく工法である。
実際の実績が無いので評価が難しいが、技術的には理屈にかなった方法であり、実現性も十分あるのではないかと思う。一つの選択肢としてありかと思う。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
最後に
いかがであったであろうか、地下室増築を考えていく際に注意しておくべき点をまとめてみた。新築時点からではあるが、地下室をつくることは地上につくる事よりは容易ではない。
法的な問題よりも、地下には地下水があったり、また半永久的に外からの力(土圧)が加わるので予想できない問題がはらんでいる可能性もある。当然、工事金額も地上部分よりはるかにかかることは考慮しておかなくてはならない。
だが、地下室を作ることに対しての技術力を日本の建設会社等は持ち合わせているので、当然つくることは可能である。
また、増築の際には建物直下に増築することはまだまだ課題がありそうであり、既存建物の平面外に増築計画をする方が現実的な計画であろう。
どちらにしろ、増築をする際の一つの選択肢として地下室増築はあるわけであるが、地上では駄目な理由をしっかり考慮した上で、地下室を作るという選択肢に踏み切った方がよいであろう。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

一級建築士
不動産コンサルティングマスター
一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。