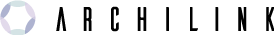避難ハッチは施設利用者が、いざという時に上階から下階に避難するために利用するハシゴを指し、共同住宅等ではこれをどこにつけるかなどたびたび議論になることが多い。
避難ハッチの位置などは、計画が進んでしまってから消防等に位置が違うと言われると躯体工事のやり直しなど、影響は非常に大きい。
ここでは、ポイントをしっかり抑えて、計画の後戻りややり直しとならないような基礎事項を確認しておきたい。
設置する必要性を考える
まず、避難ハッチとは何の為に必要であるかを考えてみたい。
結論からいうと、避難時の2方向目の避難方法である。建物は火災などが起きた時に、一方の経路が塞がれてしまうと、避難をすることができなくなってしまい一大事に至る、大原則として2方向避難という概念が存在する。
根拠法を明示するとすれば
建築基準法121条において2以上の直通階段について、消防法関係として「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」において、2方向避難型特定型共同住宅が示されている。
この法令の中で各々、2方向目の避難経路として、避難ハッチに結びつく記載がされている。
建築基準法121条3項
(略)
ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。
この記載の中で、「避難上有効なバルコニー」とい言葉が出てくる。この避難上有効なバルコニーを構成する一つの要素として、避難ハッチが存在する。避難上有効なバルコニーについては、各建築主事が基準を定めている場合があるので、その一例として下記に掲載する。
名古屋市建築基準法取り扱い基準
防火避難p58
1.令第121条第1項第三号、第六号及び同条第3項に規定する『避難上有効なバルコニーの構造等』 については、原則として次の各号に該当するものとする。
(中略)
(5) バルコニーから地上までの避難は、当該階から固定タラップ、自立式の避難はしごその他これらに類するものとすること
以下に解説を記す
上記、取り扱い基準の中における「そのたこれらに類するもの」が避難ハッチにあたる。
条文を見ることで、避難ハッチがいかなる時に求められるべきもの何ななのかをつかめたのではないだろうか。
計画を進める上では常に2方向に逃げる経路がとれているのかを念頭においておくべきである。
だが、小規模な住宅や共同住宅などでは設置義務は生じない、これもちゃんと押さえておきたいが、設置の必要性があるかもしれないと気づかなければ、うっかり計画からもれてしまう可能性がある。まずは、いるかもしれないがアプローチの方向であろう。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
計画のポイント
避難ハッチの計画の必要性がわかったところで、次は避難ハッチをどのように配置するかを考えていかない訳であるがポイントをいくつか紹介していきたい。
避難ハッチの位置は階段と反対の方向に設ける
まずは法令基準について示す。
名古屋市建築基準法取り扱い基準
防火避難p58
(1) バルコニーは、直通階段と概ね対称の位置とし、かつ、当該階の居室の各部分から容易に避難で きること
この基準は避難上有効なバルコニーの取り扱い基準であるが、避難上有効なバルコニーの中に避難ハッチを設けるので、この条文のバルコニーを避難ハッチと読みかえればよい。
直通階段は避難をするための階段であるので、同じ方向にあったのでは、火災方向に向かっていくことと同じであるので、意味がない。対称的な方向に設ける事が望ましい配置計画となる。
避難ハッチの個数は、階段に対して1個という訳ではなく消防に定める避難器具の設置個数に左右される場合もある。階段の個数の方がないのが普通であるので、それを基準に配置を考えていくことである。
また、「特定共同住宅の2方向避難型住宅」の場合は、各住戸から有事の時に階段もしくは避難器具(避難ハッチ)を使用して避難をできなければならないとしている。火災位置を想定して、どちらかに逃げれるように配置をしていく。
避難ハッチ下には避難空地を設ける
避難ハッチは上階部分から降りてくるわけであるが、地上部分に降りた地点から避難ができないようであっては問題がある。
以下のように定めているの確認をしておいていただきたい。
平成八年四月十六日 消防庁告示第二号
避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目
第二 用語の意義
五 避難空地 避難器具の降着面等付近に必要な避難上の空地をいう。
第三 避難器具の設置方法等
一 避難はしご
(二) 避難器具用ハッチに格納した金属製避難はしごは、(一)ニ、チ及びリによるほか、
次によること。
ホ 降下空間は、避難器具用ハッチの開口部から降着面等まで当該避難器具用ハッチの開口部の面積以上を有する角柱形の範囲とすること。
ヘ 避難空地は、降下空の水平投影面積以上の面積とし、避難上の安全性が確保されたものとすること。
ト 避難階の避難空地には、当該避難空地の最大幅員(一メートルを超えるものにあっては、おおむね一メートルとすること。)以上で、かつ、避難上の安全性が確保されている避難通路を設けること。
計画を進める中で、忘れてないけないポイントである。計画をしていく中で、法令遵守は当然のことであるが、特に安全にかかることは特に注意をしていかなくてはならない。
確認申請及び消防同意により、当然審査はされ不適なところは指摘を受けるわけであるが、完璧ではないことに留意してもらいたい、結局は設計者の責任あるとの意識を持ち計画を心がけたい。
共同住宅の場合などを想定して考えてみると、避難ハッチを上階から避難してきた場合に最終的には避難階である1階に到達するそこからは、バルコニー乗り越えるなどして、避難をしていく訳であるが、例えば東京都の場合などは東京都安全条例により窓先空地などの概念が存在し、普通に計画をしていけば上手くいってしまう場合などがある。
だが、窓先空地は、居室の一つが面していればよいなどの考えであるので、窓先空地を設けていないバルコニーに避難ハッチを設ける場合なども存在する訳である、そうするとうっかり緑地やブロックなどで囲んでしまい、避難不可となってしまう計画をしてしまう可能性もある。
避難ハッチの本来の目的をよく考えてみれば、避難できないという考え方はおかしいのではないかという事に気づくだろう。
法文はの読み込みは日々の業務の中で完璧にすることは難しいことである。消防署の方などの方が指導をするという立場により詳しかったりもする。法文の表面的な事だけでなく、このように指導をしている背景はなんであるのかを意識して計画しておけるようであれば尚、好ましい計画となっていくであろう。
避難ハッチの位置は、隔て板及びハッチの間隔は、600 ㎜以上確保すること
これは、消防同意の中でよく指摘をされる項目である。これはハッチ周囲に作業空間が必要であるということと、避難してきた人があけた途端にハッチがあると危険であるという観点からであろう。
よくよく考えると、常識的な認識であると思う。計画して行く中で、この認識を忘れずにして参りたいものである。
避難ハッチの構造はメーカーに確認
避難ハッチについては、消防法施工規則第27条9号において避難はしごとして定義されている。
そして「避難器具の基準」として、昭和五十三年三月十三日消防庁告示第一号において定められている。更に、通知として平成4年4月15日消防予第85号において「避難器具用ハッチの基準について(通知)」として定めているが、この基準は上蓋の腐食による問題を背景に品質を向上させることを目的に定められた。
基準は詳細に定められている。計画にあたり、消防基準に合致したものを使う訳だが、メーカーが基準に合致したものを商品化しているのでそれを積極的に用いたい。
消防に打ち合わせに行くとよくわかるが、メーカーが消防基準に合致したものをつくっているということをよく消防側は認識をしている。であるので、計画にあたりメーカーの見解をよく聞くことが近道であり正しい道でもある。
ちなみに過去の腐食問題を背景にハッチ構造の材質は溶融亜鉛メッキ鋼板やステンレスで作られている事がほとんどである。一般的には、避難ハッチの操作は上から行うことが普通であるが、上下階から操作できるものもありその用途に合わせた商品選定をしていく必要がある。
日々どのような商品が発売されているのかなどアンテナを張りめぐらせていることで、計画段階になったときに施主の要望にも迅速に対応することができるようになる。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
施工時の注意点
吊元はあっているか
設計段階でも当然話しは出てくるが,以外と注意されるので意識にいれておきたい点である。吊元を部屋側と外側とするかの議論が所轄消防の見解によって異なる場合があるので注意を要する。
ちなみに吊元を部屋側とすると、避難時において部屋側をみることになり恐怖感をいだくことなく避そ難できるという認識にもとづいているが、外側を見ている方が背中部分に壁があるという認識で安心をするという認識であるらしい。
施工段階になったら、消防署と再確認という意味で協議を行っておくのは有意義な事であり、現場検査などもスムーズに進む可能性がある。
消防設備設置計画届
東京都火災予防条例ではある特定の消防設備については設置計画届を提出することとなっている。
東京都火災予防条例
第五十八条の二 指定防火対象物等において次の各号に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第十七条の十四の規定により届け出なければならないものを除く。)を設置しようとする者は、当該設置に係る工事に着手する日の十日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
一 消防用設備等のうち漏電火災警報器、非常警報設備、すべり台、避難はしご、すべり棒、避難橋、避難用タラップ、消防用水、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備又は無線通信補助設備
設置届を出すのは当然の認識になっている場合が多いが、消防設備によっては、他の届でも出す消防署もある。これも、打ち合わせをしっかりしていれば、事前に把握することができる項目であるので、しっかりと打ち合わせを重ねていきたい。
消防に相談
消防署の考えは当然、法にのっとり指導してくることは当然であるが、いざ火災といった時の実情を考えた指導をすることが多い。
建築主事などはどちらかというと、ゆうじに救助に行くという立場ではないので、なかなか現場の実情に合わせた指導というものは難しかったりする。しかし消防は有事において自身が救助、鎮圧に向かう立場であるとの認識で指導をしてくることが多い。
設計者としては、この姿勢に対しては誠実に対応しなければならない、消防の方も、設備を一つ多く要求することは、予算アップにつながるであろうとの立場は理解して発言してくることが多い。
よくよく消防署と施主を含めた中での施設安全に対する協議はしておかなければならない。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
最後に
いかがであったであろうか、避難ハッチの基本的部分をまとめてみた。
建築計画は最終的には設計者の責任の元に計画を行うことを常に認識をしておかなければならない。上記の部分でも、何度も打ち合わせが重要であると言っているが、これはただ打ち合わせをすれば良いというものでもない、このコラムなどを通して知識を深めた中で打ち合わせをしていかないと相手が全てを言ってくれる訳ではないので、うっかり漏らしてしまうことも十分にありうる。
指導する側としては、当然のことのようにわかっているだろうとの認識で話を応答することも多い。建築確認や消防同意という言葉を考えるとよくわかるが、認定をしているわけではない。あくまで建築確認は問題ないことを確認したに過ぎず、消防同意は計画を一応確認して見ましたよという程度の話である。
であるので、なぜ確認申請の時に指導をしてくれなかったんだという意見を言いたくなるかもしれないが、それは通用しないという認識の方が正しいであろう。間違った考え、間違った解釈をを誰かが正してくれるとは限らない。自身で幾度となく見直し確認するという行為は重要なことである。
結局は設計者は建築士自身であり、施工者は施工者自身や消防設備士などであり、責任はそこにあると認識するのが妥当な考え方である。日々たゆまぬ知識を身につけいざという時に正しい判断をできるように、さらなるスキルアップを目指し業務発展に努めていきたいものである。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

一級建築士
不動産コンサルティングマスター
一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。