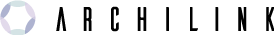非常用エレベータについては、建築専門家以外の一般の人々にはなじみの薄い建築設備かもしれない。また建築設計の世界でも、高層の建築物に設置が必要となる設備であることから、これまで設置した経験のない方も少なくないのではないだろうか。
とはいえ、日常で非常用エレベータを目にする機会は実は多い。たとえばデパートなどの商業施設では非常用エレベータを客用と併用することも多い。またタワーマンションが増えてきた昨今では、日常的に使用しているケースも多いだろう。
ここでは、非常用エレベータについて、その設置基準や緩和規定などを解説する。
非常用エレベータとは
まず非常用エレベータとは何か、その定義について確認しよう。
ここで解説する設備は、建築基準法第34条第二項に定められた「非常用の昇降機」のことをいう。以下に確認すべき条文をまとめる。
設置基準 建築基準法 第34条第二項
非常用の昇降機の設置を要しない建築物 建築基準法施行令 第129条の13の2
非常用の昇降機の設置及び構造 建築基準法施行令 第129条の13の3
以下、上記の条文を参照しつつ、解説していこう。
なお、建築基準法上での呼称は非常用の昇降機であるが、建築基準法施行令で昇降機をエレベーターと再定義しており、また呼称として一般的であることから、この解説では非常用エレベータの呼称で統一する。
一般の人々が「非常用エレベータ」と聞くと、避難用のエレベータを連想するかもしれないが、法の主旨としては本来、火災などの非常時に、消火・救助活動等に使用することを想定したエレベータである。
高層建築物の高層階において火災等が発生した場合、低層建築物と同様のはしご車等を使用した消火・救助活動には困難が想定される。そこで、建築物内部の昇降設備を消火活動に使用する目的として、設置が要求されるものである。消防隊がはしご車等で火災箇所にアプローチするのではなく、エレベータに乗りこんで火災箇所に向かうわけである。
そのため、非常用エレベータには、内部に専用の制御装置や通信設備を設け、扉を開いたままの状態でも昇降できるようにするなど、非常用としての特殊な構造・設備が必要となる。建築基準法施行令第129条の13の3に詳細な規定があるので、以下に一部抜粋する。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
建築基準法施行令 第129条の13の3
第七項 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
第八項 非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。
第九項 非常用エレベーターには、第129条の8第二項第2号及び第129条の10第三項第2号に掲げる装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。
(後略)
このように、通常のエレベータとは異なる制御装置等が必要となる。とはいえ、各メーカーにおいて、この規定を満足するような非常用エレベータが商品化されているので、設計者としてはメーカーと打ち合わせのうえ、適切な機器を選定すれば事足りる。
また、エレベータだけではなく、乗降ロビーや電源設備など、設備以外の部分においても様々な規定がある。簡単にまとめると、乗降ロビーは消防隊の一時待機場所としての、ある程度の面積を持ったスペースとその区画、排煙の確保が要求され、火災時の停電でも停止することのないよう、非常用の予備電源が必要とされる。
こちらのほうはメーカー任せにすることはできない。設計者として対応が必要となるため、次項で具体的な内容を解説する。
これらのことから、非常用エレベータがほんらい消火・救助活動等に供するものであるということが理解できる。このことは後段で解説する、設置緩和を理解する上でも重要となるので、しっかり確認しておきたい。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
非常用エレベータが必要な建築物
非常用エレベータの設置が必要となる建築物の規定は、建築基準法第34条第二項にその規定がある。以下に条文を示す。
建築基準法 第34条第二項
高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
この条文で言うところの、高さが31mをこえる建築物が、前項で解説した高層建築物ということになる。この規定は消防法第8条の2で定める、消防法上の高層建築物の定義とも合致することはあわせて確認しておいてほしい。
また、設置台数については、31mをこえる部分の床面積に応じて設置台数が決まる。建築基準法施行令第129条の13の3第三項ホで定められているが、31mをこえる階の床面積が1,500㎡以下の場合は一基、1,500㎡を超える場合は3,000㎡ごとに一基ずつ加算される。
また、条文ではこの規定にもとづき二基以上の非常用エレベータを設置する場合、「避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。」とあることに注意が必要である。この間隔については法の規定はなく、行政及び審査機関との協議が必要となるが、二基を並べるかたちでの配置は認められないと考えておいたほうがいいだろう。
前項でもふれた、乗降ロビー等についての基準についても施行令の同条文に規定がある。以下に一部抜粋する。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
建築基準法施行令 第129条の13の3
第三項 乗降ロビーは、次に定める構造としなければならない。
(中略)
4 窓若しくは排煙設備又は出入口を除き、耐火構造の床及び壁で囲むこと。
(中略)
6 予備電源を有する照明設備を設けること。
7 床面積は、非常用エレベーター一基について10㎡以上とすること。
8 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること。
(中略)
第五項 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第三項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員4m以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
(中略)
第十項 非常用エレベーターには、予備電源を設けなければならない。
(後略)
本条文にはほかにも詳しい規定があるため、確認しておいていただきたい。面積の基準や排煙、歩行距離などにより、平面上の配置計画で制限がある。また消火設備の位置や予備電源など、設備関係の調整が必要となることが理解できるだろう。
このように、非常用エレベータはまず設備として特殊なため、相応のイニシアルコストが必要となる。それだけではなく、乗降ロビーに要求される規定から、その面積・位置などが限定され、計画上の制限となってくる。また、無視できないのが、予備電源などに必要となる、保守・点検などのランニングコストの発生である。
これらは単に継続的な負担となるだけでなく、万一不備があった場合に責任が発生するリスクともなりうる。
計画によっては、これらの要素は大きな負担となりうるため、非常用エレベータの有無は計画上おおきな意味を持つ。そこで重要な検討項目となるのが、つぎに解説する緩和規定である。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
非常用エレベータの設置が免除される建築物
前項で引用した、建築基準法第34条の条文に「政令で定めるものを除く」とあるように、建築基準法施行令第129条の13の2において、非常用エレベータの設置に関する緩和規定が定められている。以下に一部抜粋する。
建築基準法施行令 第129条の13の2
法第34条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
2 高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下の建築物
3 高さ31mを超える部分の階数が四以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(中略)で区画されているもの
4 高さ31mを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
ここで、最初に解説した、非常用エレベータが消火・救助活動等に使用するものであるということを思い出してほしい。31mをこえる部分については、通常の消火活動が困難となるため、非常用エレベータが必要となる。
ではもし、31mをこえる部分であっても、その部分について火災のおそれが少なかったり、さほど消火活動が困難でなければ、非常用エレベータの必要性は低くなると考えられる。条文にある四つの項目がそのような条件に合致していることが理解できるだろう。
各条文については一読して理解できる内容であるが、ここでは特に共同住宅などで活用する機会が多い、第3号について解説をくわえる。
大規模な共同住宅では15階建てが多くみられるが、実はその要因の一つがこの緩和規定による。つまり、非常用エレベータの設置が免除される範囲で、最大の階数(すなわち住戸数)となるような計画となっているのだ。
一般的な共同住宅の階高では、おおむね11階部分で31mをこえる。そこからさらに階数四をくわえると15階建てとなる。また、ふつう各住戸ごとに区画されているため、第3号の緩和規定を満足することになる。したがって、15階建ての共同住宅は多くみられるものの、16・17階建ては少ないということになるわけだ。
ここで注意したいのが、31mをこえる階の定義だ。法規上は厳密な規定がないが、一般的には31mのラインが、その階の「階高の1/2」よりも下にあれば、その階は31mをこえると判断される。たとえばある建築物の11階のレベルが地盤面から29.5m、12階のレベルが32.4mであった場合、11階の階高の1/2は地盤面から30.95mとなるので、11階は31mをこえる階ではない。
これについては階高の基準となるレベルも含め、行政及び審査機関への確認が必要となる。また、高さ31m以下の階の階高もふくめた断面計画が重要である。さらに、設計を進める過程で、階高や地盤面レベルの変更があった場合、斜線制限などの高さチェックはするものの、階高の1/2のチェックについては忘れがちなので、注意が必要だ。
これは余談になるが、とくに共同住宅の業界関係者、ときには設計者でも「15階までは非常用エレベータが不要」と勘違いしている場合がある。はしご車も消防活動空地を適切に配置すれば15階まで到達できる場合もあるので、これも紛らわしい。とはいえ言うまでもないが、先に条文を引用した通り、非常用エレベータの設置は31mが基準である。15階は緩和規定から生じた数字にすぎない。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF
最後に
ここまで、非常用エレベータについて、その内容、設置の条件、そして緩和規定について解説してきた。非常用エレベータは火災などの非常時には重要な設備であるが、コスト面や相応の床面積が必要となることから、設置が免除されるかどうかの検討は重要である。
とくに前項で解説をくわえた施行令第129条の13の2 第3号の規定については、低層階の階高もふくめた、基本計画段階からのチェックが必要となるので、早い段階で検討しておきたい。
活用することによって計画・コスト面で合理化をはかることのできる緩和規定であるが、非常用エレベータを必要とするような危険性が小さいことにより設置が免除されるものであることは、ここまでの解説で理解できるだろう。決して建築物の安全性とトレードオフで免除されているわけではないということは理解しておけば、クライアントへの説明もスムーズにできることと思う。
→無料プレゼント『知らないと恥を書く!建築関係者が絶対に知っておくべき法令大百科』PDF

一級建築士
不動産コンサルティングマスター
一級建築士としての経験を活かした収益物件開発、不動産投資家向けのコンサルティング事業、及びWEBサイトを複数運営。建築・不動産業界に新たな価値を提供する活動を行う。